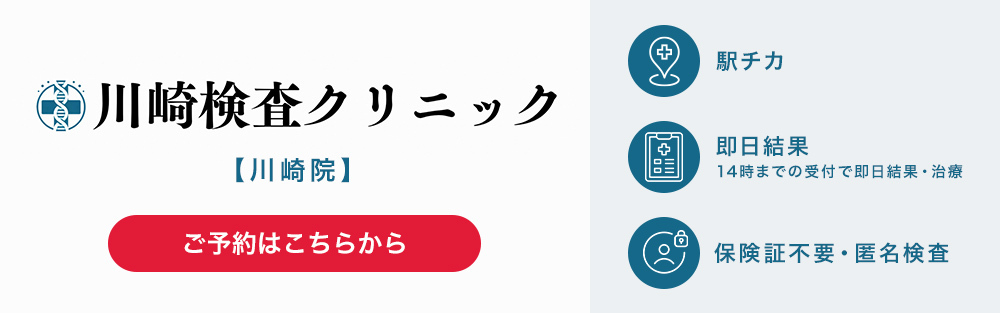梅毒について
梅毒は、梅毒トレポネーマ(Treponema pallidum)という細菌によって引き起こされる性感染症です。
昔は不治の病と言われていた梅毒でしたが、【ペニシリン】が発見されたことで治療が可能な病となりました。
現在では適切な治療を受けることで完治する病です。
しかし、感染を放置すると全身に影響を及ぼす重篤な合併症を引き起こすことがあります。
最悪の場合は命を脅かす可能性があることに変わりはございませんので、
早期発見・早期治療が望ましいです。
梅毒の症状 ※一部厚生労働省HPより抜粋
梅毒は【偽装の達人】という異名を持つほど、その他の感染症・疾患への擬態が上手な感染症です。
そのため症状のみで梅毒か否かの判定をするのはまず不可能です。
梅毒の感染については検査が必須となりますのでご注意ください。
Ⅰ期顕症梅毒:感染後数週間
梅毒トレポネーマが侵入した部位(主に口の中、肛門、性器等)に、
しこりや潰瘍ができることがあります。
また、股の付け根の部分(鼠径部)のリンパ節が腫れることもあります。
※特に症状のない無症状の方も多くいらっしゃいます
これらの症状は痛みを伴わないことが多いです。
治療をしなくても症状は自然に軽快しますが、ひそかに病気が進行する場合があります。
Ⅱ期顕症梅毒:感染後数か月
感染から3ヶ月程度経過すると、梅毒トレポネーマが血液によって全身に運ばれます。
この時期に、
小さなバラの花に似ていることから「バラ疹(ばらしん)」とよばれる淡い赤い色の発疹が、
手のひら、足の裏、体幹部などに出ることがあります。
その他にも肝臓、腎臓など全身の臓器に様々な症状を呈することがあります。
発疹などの症状は、数週間以内に自然に軽快しますが、梅毒が治ったわけではありません。
また、一旦消えた症状が再度みられることもあります。
アレルギーや他の感染症などとの鑑別が重要であり、適切な診断、治療を受ける必要があります。
晩期顕性梅毒:感染後数年
感染後数年程度経過すると、
ゴム腫と呼ばれるゴムのような腫瘤が皮膚や筋肉、骨などに出現し、
周囲の組織を破壊してしまうことがあります。
また大動脈瘤(だいどうみゃくりゅう)などが生じる心血管梅毒や、
精神症状や認知機能の低下などを伴う進行麻痺、
歩行障害などを伴う脊髄癆(せきずいろう)がみられることもあります。
現在では、抗菌薬の普及などから、晩期顕性梅毒は稀であるといわれています。
神経梅毒
感染が脳や脊髄に及んだ場合を神経梅毒と呼び、どの病期でも起こりうるとされています。
梅毒が疑われる症状や感染の心当たりがあれば、
病期にかかわらず早めに医療機関を受診するようにしましょう。
梅毒治療について
梅毒の治療には、抗菌薬(主にペニシリン系)を用います。
病期(第1期〜第4期)や全身状態によって、治療内容や期間が異なります。
治療の判定は、定期的な血液検査(RPR・TPHAなど)で治療効果を確認します。
感染拡大を防ぐため、パートナーの検査・治療も重要です。
症状が消えても、検査上の数値が陰性化するまでには数ヶ月〜1年程度かかることがあります。
医師の指示に従い、最後までしっかりと治療を続けましょう。
早期梅毒(第1期・第2期)
通常、ペニシリンGの筋肉注射(1回または数回)、
またはアモキシシリンなどの内服薬による治療を行います。
晩期梅毒(第3期以降)や神経梅毒
より長期間の治療や点滴による投与が必要になることがあります。
ペニシリンアレルギーがある方には、代替の抗菌薬を使用します。
※晩期梅毒や神経梅毒については当院での治療ができかねる場合がございます。
当院提携の病院に紹介状を書かせていただく可能性がございます。
治療方法
梅毒は内服治療と、注射治療と2種類ございます。
どちらもメリット・デメリットがございますので、
患者様のご希望も尊重しつつ、最終は医師と相談の上で治療方法を決定いたします。
それぞれの治療方法について詳しく解説いたします。
内服治療
内服治療では主にアモキシシリン(サワシリン)というお薬を約1ヶ月間内服を行います。
ペニシリンに対してアレルギーのある方は、ドキシサイクリン(ビブラマイシン)等で治療を実施することもあります。
【メリット】
・注射治療より金額を抑えられる可能性がある。
・内服になるので、体調不良時の休薬がしやすく、副作用のコントロールがしやすい。
【デメリット】
・長期間の間、朝昼晩の内服を毎日継続しないといけないので煩わしく感じる事がある。
・他人に内服を見られる可能性がある。
比較的メリット・デメリットのバランスが取れているのが内服治療の良い所かもしれません。
注射治療
注射治療では持続性ペニシリン筋注製剤のベンジルペニシリンベンザチン水和物(ステルイズ®)を、
臀部へ1回だけ筋肉注射を行います。
後期梅毒の場合は3回筋肉注射を行う場合がございます。
【メリット】
・1回の注射で治療が完了するので負担が少ない。
・内服のように飲み忘れの心配がない。
・他人に気付かれる心配がない。
【デメリット】
・料金が内服治療に比べて高くなる。
・内服に比べてアレルギーや副作用のコントロールがしづらい。
※投与後に重大な副作用が発生しないか、投与後30分程度は院内で経過観察を行います。
・18ゲージの太い針で筋肉注射を行うため、痛みが生じる可能性がある。
注射治療はメリットも多い分、少なからずリスクの伴うものになりますので、
ご不安な点があればお気軽にご相談ください。
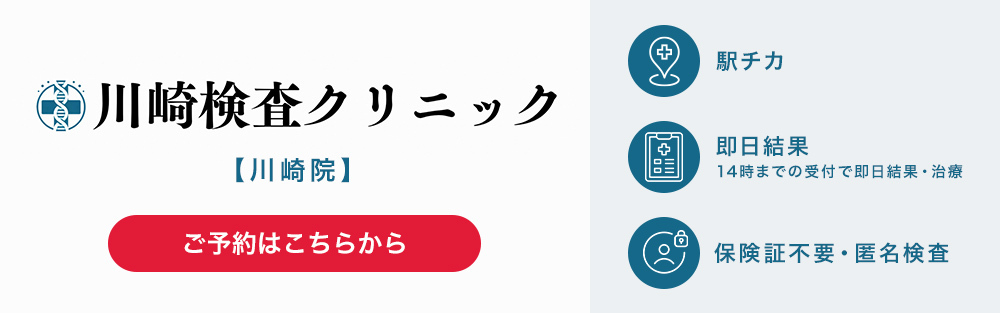
当院での流れ
採血による梅毒検査を受けていただきます。
当院では【梅毒TP抗体・梅毒RPR】の2項目の血液検査を受けていただきます。
梅毒はこの2項目で感染の判定を行います。
片方だけでは感染の有無を判定できないため、原則2項目受けていただきます。
他院様で既に検査を受けられている場合であっても、
検査機関により結果・数値が異なる可能性があること、正しい治療経過が辿れないため、
治療と同時に当院でも採血検査を実施して頂く可能性がございます。
予めご了承くださいませ。
上記に記載の通り、2つの項目の結果で感染の判定を医師が行います。
梅毒の結果は様々な組み合わせがあり、直近の性交渉歴や持病等の有無を加味しながら、
現在の感染の有無や、既往の判断をします。
例:
TP抗体-(陰性)・RPR-(陰性) → 非感染・感染極初期
TP抗体-(陰性)・RPR+(陽性) → 梅毒初期・生物学的偽陽性(自己免疫疾患等)
TP抗体+(陽性)・RPR-(陰性) → 梅毒既往・感染極初期
TP抗体+(陽性)・RPR+(陽性) → 活動性梅毒・梅毒治療中
上記の結果はあくまでも参考程度になります。
ご自身での判断は難しいので、いずれか1つでも陽性が出た場合は医師にご相談ください。
医師より治療が必要と判断された場合は、
内服治療か注射治療を実施いたします。
【内服治療】
1日3回の内服を2週間以上継続する必要があります。
【注射治療】
一回の注射で終わりますので2週間の内服が負担と感じる方は、『注射』がおすすめです。
※医師とも相談の上、患者様のご希望に極力添えられるようにはいたしますが、
内服治療・注射治療お選びいただけない場合もございます。
治療終了2~4週間後を目安に再検査を実施いたします。
数値の減り具合を見て治療終了・治療継続の判定を医師が行います。
ご自身の判断で治療を終了しないようにご注意ください。
※治療後の再検査(1回)はご料金は発生いたしません。
治療が終了となった場合も、
しばらくの間は約3ヶ月毎を目安にフォローアップ検査を受けるようにしてください。
※数値が下がりきらない場合など、高次医療機関へのご紹介になる場合がございます。